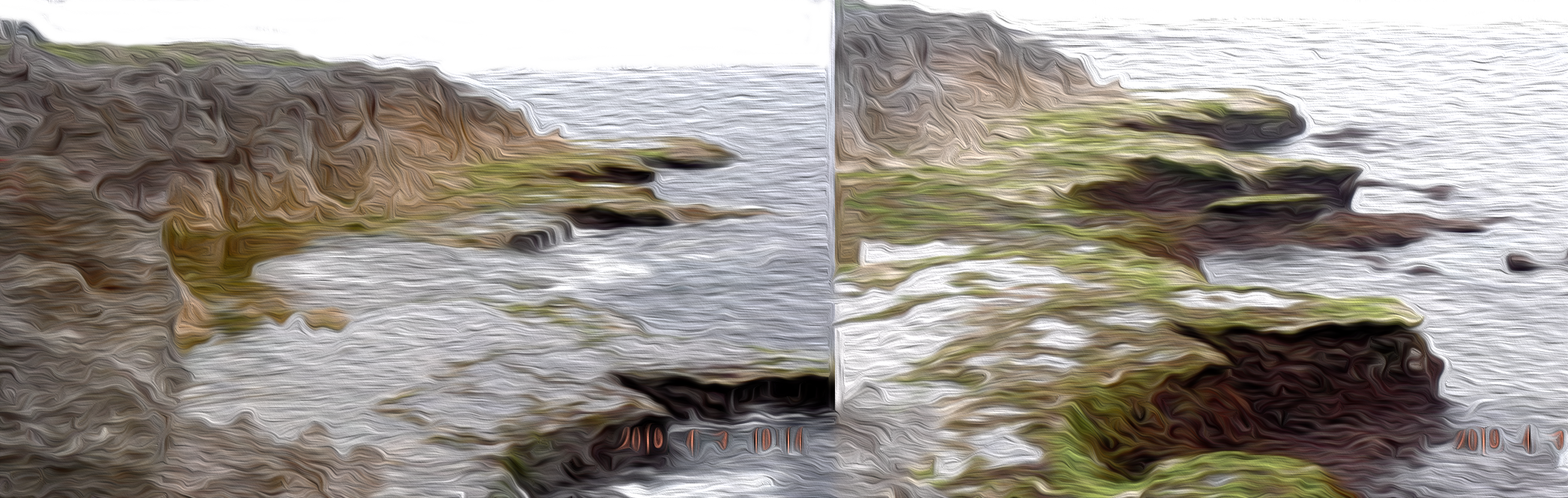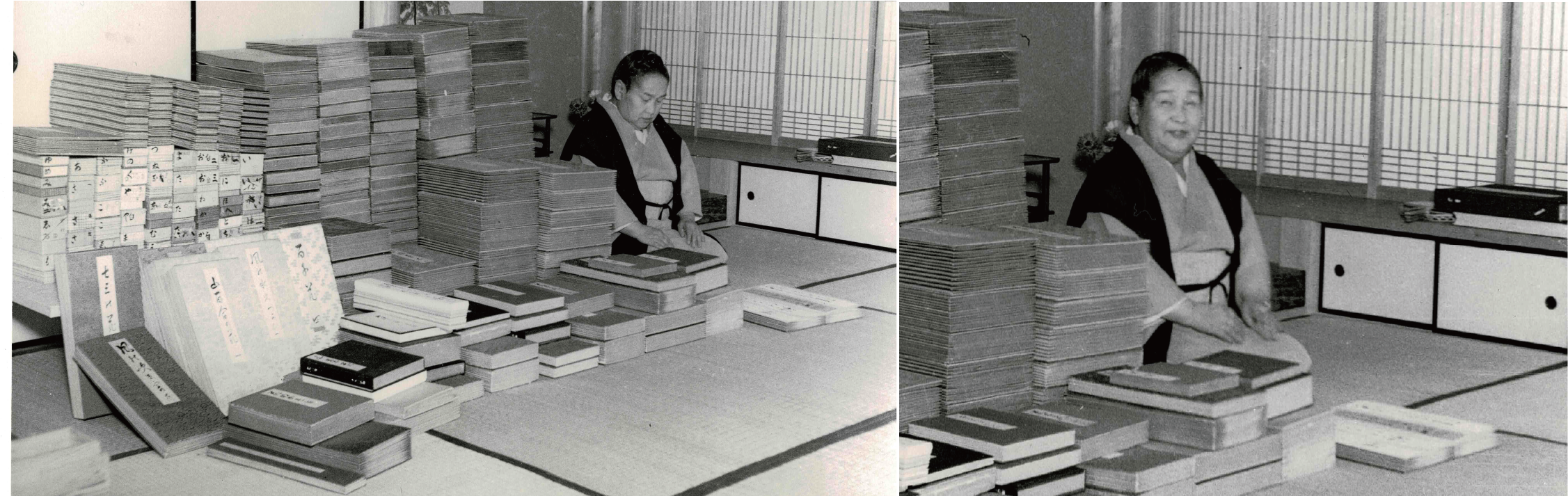呪われたairpods左 the damnatory left one of airpods
5月連休中にタニハ庭での伐採中,airpodsの左を紛失し,再購入となった。次の記事に示している。My left airpod (2nd generation) was lost in the field, and i had been grappling with some difficult problems 先ほど,また目の前で紛失した。比較的高い本立と低い試料ケースの間に,カランコロンと落ちた。探しても探してもない。前に紛失した後,「探す」=searchというソフトをiPhoneにインストールしていたので,残りのairpod右はケースに入れて蓋をして,「探す」を立ち上げた。 どうも紛失したairpodsから音を出す機能があるらしい。すぐそばで鳴っている。しかし,ぼくは15年ぐらい前に突発性難聴になって以来,音源の位置を捉えることが難しい。奥さんを呼んで聞いて貰った。隣接の本箱と壁の僅かな隙間には,ファイルケースなどが何故か入っている。それを何とか取り出して,そして,最も隅っこにあった。 このあと,綿ぼこりなどを掃除して,疲れてしまった。Jun. 13, 2020